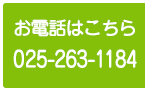2025/11/02
Basic course2025への参加 世界基準の根管治療を目指して⑥
新潟市西区 歯周病専門医 いとう歯科診療室のホームページをご覧頂きありがとうございます。
今回は6回目「再根管治療の意思決定と実際」についてでした。
「なんか根っこの先の方の歯ぐきが腫れて、つぶれました、長い間くりかえしています。」
よくある患者さんの主訴のひとつ。根尖病変からの膿の出口、いわゆるサイナストラクトがある状態。
前医で根管治療を受けていたが、再発した場合の対処法について学びました。
1回治療を受けて再発しているので、大体の場合が治療の成功率は低下しますが、そのなかでも再治療によって治癒が見込めるケースとそうでないケース、について理解を深めることができました。
要はやみくもに再治療するのではなく、ケース選択が重要になります。根管治療が充分に行われていない場合、未処置の根管がある場合、根管治療後の補綴処置(被せ物)があまい場合、などは再治療の価値があるかもしれません。もっと分類がありますが、ここでは省きます。
逆に再治療では厳しいケースは、前医が一生懸命治療しようとして、根管形態が保たれてない場合、根管に穴が空いている場合、根尖が破壊されている場合、などです。
なにしろ、口という狭い視野で、根管という見えない部分を治療するので、優秀な歯科医師でもこのようなトラブルは治療と隣り合わせなのです。なのでアメリカでは高額なのです。
むし歯も歯周病も、そして根尖病変も、歯科における病気は細菌感染症です。
根管治療後に補綴処置があまいと、隙間から細菌感染し、根尖病変にまで至ることもあります。根尖病変からは大腸菌が検出されるというのも驚きです。
ほんとはしっかりした根管治療を受けたら、精密な補綴が必要になります。
これを保険で行っていくのはかなり困難など感じています。
また、「歯ぐきが腫れて、つぶれて、を繰り返しています」という状態。
口腔内から膿の出口を通して、細菌は根尖に行ったり来たりフリーパスの状態になるので、根管治療での治癒率が著しく低下します。
長期間の放置はその歯を根管治療で治癒に導くには難しくなることを理解して欲しいと思います。
ただ、症状にでることは少ないので、残念ながら放置しがちです。
再治療で治癒するかもしれない!となっても、テクニカルに困難なことが多いのです。
装着された土台の除去、根管内に充填された薬の除去、再根管形成や、根充方法について学びました。
次回は7回目、上記のテクニカルな部分の実習になります。
どれくらい早く土台が除去できるのか、楽しみ。